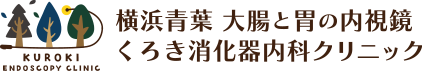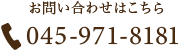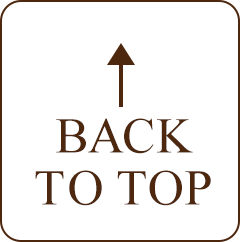ピロリ菌とは
 ピロリ菌は正式には「ヘリコバクター・ピロリ」と言い、胃の粘膜に生息するらせん状の細菌のことを指します。
ピロリ菌は正式には「ヘリコバクター・ピロリ」と言い、胃の粘膜に生息するらせん状の細菌のことを指します。
胃の中には強い酸(胃酸)があるため、通常は細菌が生存できませんが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を使って胃酸を中和し、自らが生存できるアルカリ性の環境を作り出します。
ピロリ菌の感染経路はまだ完全には解明されていないものの、大部分のケースは経口感染であると考えられています。
ピロリ菌への感染率は幼少期の衛生状態と関係があるとされ、上下水道が十分に発達していなかった世代ほど感染率が高いと言われています。
ピロリ菌の症状
胃の中にピロリ菌がいると、多くの方が自覚症状のないまま胃炎を起こしています。
胃の病気にかかると、胃もたれ、胸焼け、空腹時や食後の胃痛、食欲低下などの不快な症状が現れます。その他、喉の違和感(つまり、いがいが感)や声のかすれなど、食道以外の症状を伴うこともあります。
ピロリ菌と関係する
病気について
ピロリ菌に感染すると胃に炎症が起こり、この炎症が長引くと慢性胃炎になります。
加齢とともに炎症が進むと、胃粘膜の委縮や腸上皮化生が起こり、萎縮性胃炎という状態になります。この萎縮性胃炎から胃がんの発症が多いことがわかっています。
また、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症や再発にもこのピロリ菌の感染が関わっていることが知られており、潰瘍の患者さんでは80~90%と極めて高い感染率を示します。
その他にもさまざまな病気とピロリ菌は関連があります。
ピロリ菌の原因
ピロリ菌の感染経路はまだ完全には解明されていませんが、口から菌が入り胃に感染する経口感染ではないかと考えられています。
ピロリ菌の感染ルート
幼少期にはさまざまなものを口にするため、衛生環境や飲料水からピロリ菌が体内に入ると考えられています。幼児期の胃の中は酸性が弱く、ピロリ菌が生き残りやすい環境にあるようです。ピロリ菌が幼児期に感染すると言われているのはそのためです。日本では60歳以上の半数以上が感染しており、東南アジアでは衛生環境の悪い地域ではほぼ全員が感染していると言われています。また、ピロリ菌は家庭内での母子感染が疑われているため、食べ物を口移しであげることなどには注意が必要です。
ピロリ菌の検査
胃カメラを使用する検査
迅速ウレアーゼ試験
胃カメラを使って、小さな組織片を採取します。それを特殊な検査液に入れて色の変化を見て判定します。この検査では、ピロリ菌が生成する、尿素を分解する酵素ウレアーゼの活性を利用します。
鏡検法
胃の粘膜の組織標本に特殊な染色を施し、顕微鏡で直接ピロリ菌を探します。
培養法
胃の粘膜を採取し、ピロリ菌が発育する環境下で5~7日間かけて培養し、その後判定をします。
胃カメラを使用しない
検査
抗体検査
細菌に感染すると、体の中で抗体が作られます。ピロリ菌に感染した際にも同様に抗体が作られるため、この抗体の存在を血液や尿を採取して確認することで感染の有無を調べます。
尿素呼気試験
容器に息を吹きかけることで呼気を調べる検査です。尿素の検査薬を飲んでいただき、薬を飲む前と飲んだ後に呼気を採取して診断します。ピロリ菌のウレアーゼという酵素が尿素を分解して二酸化炭素とアンモニアを生成するため、呼気中の二酸化炭素の量からピロリ菌の有無を判定します。この検査は、直前の食事制限はありますが、体に負担がかからず、精度の高い検査です。
糞便中抗原測定
便の中にピロリ菌の抗原があるかないかを調べる方法です。この検査も体への負担がありません。
当クリニックでは尿素呼気試験、迅速ウレアーゼ試験、抗体検査の3つの検査を主に実施しています。特に胃がんは日本人に多いので、胃カメラ検査とこれらの検査を同時に受けることをおすすめしています。
ピロリ菌の治療(除菌)
ピロリ菌感染が確認された場合は、担当医と相談の上、除菌治療を受けるかどうかを検討してください。
ピロリ菌の除菌療法は、「胃酸の分泌を抑制する薬」を1つと「抗菌薬」2つの計3つの薬を7日間服用していただきます。除菌治療を終えた後、1ヵ月(4週間)以上間隔を空けて、再度ピロリ菌が除菌されたかどうか検査を受けていただき判定します。
除菌療法の成功率は
どれくらい?
服用を正しく行えば、最初の治療(一次除菌)の成功率は約80%と報告されています。
一次除菌でピロリ菌が除菌できなかった場合、抗菌薬を一部変更し、再度除菌治療(二次除菌)を行います。
一次除菌でピロリ菌が除菌できなかった場合でも、二次除菌療法を適切に行えば、ほとんどの症例で除菌に成功するといわれています。
ピロリ菌のよくある質問
健康保険を適用してピロリ菌を除菌することはできますか?
半年以内に胃カメラ検査を受けており、慢性胃炎(萎縮性胃炎)と診断されている方はピロリ菌の除菌療法は保険適応となります。
一次除菌、二次除菌は保険適応となりほとんどの方が除菌に成功しますが、ごく少数の方は除菌がうまくいかないことがあります。その場合の三次除菌は自費になります。
ピロリ菌除菌の副作用にはどのようなものがありますか?
除菌療法の主な副作用は以下の4つです。
- 軟便・下痢:抗菌薬による腸内細菌のバランス変化が原因
- 味覚異常:食べ物の味がおかしく感じる、苦味や金属の味がする
- 肝機能の検査数値変動:AST(GOT)およびALT(GOT)値の変動
- 発疹・かゆみ:薬剤によるアレルギー反応で発疹やかゆみ
これらの副作用がひどく生じた場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。
ピロリ菌を除菌した後、菌が消えたかどうかはどうすればわかりますか?
除菌治療を終えた後、1ヵ月(4週間)以上間隔を空けて尿素呼気試験を受けることで、除菌されたかどうかを調べることができます。
ピロリ菌の検査や治療費用はいくらですか?
胃カメラ検査で胃炎や胃潰瘍などと診断されている場合は、保険が適用されますので、ピロリ菌検査・治療の自己負担額(3割負担)は診察料等含めて約6,000円~7,500円となります。
「ピロリ菌の有無を調べたい」「胃がん予防のためにピロリ菌検査を受けたい」という理由での受診の場合、公的医療保険は適用されません。
この場合は自由診療で全額自己負担となり、検査のみで1万円前後、検査と除菌治療で2万円前後が目安となります。
ピロリ菌は必ず除菌しなければいけないのですか?
潰瘍を繰り返すなど、ピロリ菌をしっかり除菌した方が良い場合もありますが、他に大病をお持ちの方や、除菌治療による副作用が起こったり、何度やってもピロリ菌が除菌できない場合などは、その限りではありません。医師と相談の上、ご自身に合ったやり方を探していきましょう。